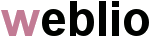学研全訳古語辞典 |
連歌
分類文芸
詩歌の形式の一つ。五・七・五の長句と七・七の短句とを別人が交互に詠んで連ね、一つの作品とする合作文芸。和歌から派生して、平安時代末期から室町時代末期に盛んに行われた。初めは、長句・短句を二人で詠み合って一首とする「短(たん)連歌」であったが、平安時代末期から、長句・短句を詠み継いで連ねる「長(ちよう)連歌(=鎖(くさり)連歌)」が作られた。ふつう、「連歌」といえば、この長連歌をさす。長連歌は、百韻(=百句)を標準の形式とするが、五十韻・歌仙(=三十六句)・千句・万句などもある。第一句を発句(ほつく)、第二句を脇(わき)、第三句を第三、最終句を挙句(あげく)、他の句を平句(ひらく)という。普通は数人が共同で一つの作品を作る。作品は句と句の付け方を中心とした、一編の変化のおもしろさが重んじられた。鎌倉時代には、滑稽(こつけい)を主とする無心(むしん)連歌(=栗(くり)の本(もと))と、優美な詠みぶりの有心(うしん)連歌(=柿(かき)の本)とに分かれていたが、室町時代になって二条良基(よしもと)・心敬(しんけい)・飯尾宗祇(いいおそうぎ)らのすぐれた連歌師が現れ、芸術として完成した。宗祇以後も盛んに行われたが、形式や規則(式目)が複雑になって衰えた。しかし、次の時代の「俳諧(はいかい)の連歌」のもととなった。「筑波(つくば)の道」とも。⇒長連歌
参考
連歌の起こりは、『古事記』にある、倭建命(やまとたけるのみこと)と御火焼(みひたき)の翁(おきな)との唱和「新治(にひばり)・筑波(=ともに地名)を過ぎて幾夜か寝つる」〈新治、筑波を通り過ぎていったい幾晩寝たことか。〉「かがなべて夜(よ)には九夜(ここのよ)日には十日を」〈日数を重ねて、夜は九晩昼は十日であることよ。〉と考えられた。連歌を「筑波の道」というのは、この唱和に基づいている。
| 連歌のページへのリンク |